そのまま覆い被さるようなことはせず、オスカーはアンジェリークの足許に跪いてまず履物を脱がせた。
「オスカーさま?…」
いつもと違うオスカーの振る舞いにアンジェリークはやはり戸惑い気味だった。
「いいから、そのままで…お嬢ちゃん…」
自分は足が埋まりそうなほど毛足の長い絨毯に膝立ちして、オスカーはアンジェリークの身体から一枚一枚果実の皮をむくように丁寧に衣服を取り去っていった。
まさに傷つきやすい果実を扱うような繊細な手つきだった。
その一方で自分の衣服は無頓着に毟り去るように脱ぎすてていく。
アンジェリークをレースのランジェリー姿にしたところで、オスカーは露になった真白い腿に手をのばし絹の靴下を脱がせた。
すんなりとしたあいらしい素足が現れると敬虔とも言える仕草でそっと足の甲に口付けた。

「あ…」
アンジェリークはまだオスカーの意図が汲めずにどうふるまっていいかわからなかった。
部屋に入るまでは強引とも思える態度だった。性急に組みしかれるものと思っていた。
だがその態度は今は一転し、まるでプリンセスに仕える様にオスカーは恭しいとも言える態度でアンジェリークに傅いていた。
なにやらそれが無性に気恥ずかしく思わず足を引っ込めようとしたが、オスカーに足首をしっかり握られてしまい果たせなかった。
「お嬢ちゃん、動かずに…ただ、俺の想いをあるがままにうけとめてくれ…」
オスカーはアンジェリークの足の指のひとつひとつにキスを落としては軽く舐っていく。
アンジェリークは背筋を這い登るようなこそばゆさに耐えて息を詰めた。
両の足指のすべてに口付けてしまうと再び足の甲に唇を押し当て、その唇をそのまま上へと滑らせて行く。
張りのある脹脛に軽く歯をたててから舌でなめあげるとアンジェリークが一瞬息を飲む気配を感じた。
手で挟みこむようにすらりと伸びた足をなでさすりながら、唇は膝を抜けて豊かにはりのある太腿に達しようとしていた。
オスカーはアンジェリークの膝頭を掴んで足を大きく割ると自分の体をその間に滑りこませた。
アンジェリークが反射的に足を閉じようと膝に力をこめたのを感じたので、一度身体を起してなだめるように唇に軽く口付けた。
口付けにアンジェリークの身体が柔らかくほぐれた。
オスカーは改めて血管が青白く透けて見えそうに白い太腿に唇を滑らせて行く。自分は跪いたまま、アンジェリークに慈悲を請うような恭しい態度を崩さずに、内股に舌を這わせていった。
内股の筋肉にさっと緊張が走ったのをオスカーの唇は感じ取った。だが、アンジェリークはもう膝に力をこめようとはしなかった。
オスカーはアンジェリークの許容を感じ穏やかに慰撫するように足のあらゆる部分に舌を這わせつづけた。
そしてアンジェリークはオスカーが自分の足が順を追って舐っているところをじっと見おろしていた。というより目が離せなくなっていた。
オスカーが舌で描いていく唾液の軌跡がひいやりと肌から熱を奪っていっているはずなのに、オスカーの唇が触れたところは逆に火照るように熱くなっていく。
オスカーは自分に動かずにと言った。これからどうする気なのだろう。期待と僅かな不安に胸がきゅっと締め付けられる。
オスカーは腿の付け根の部分まで舌を伸ばしたところで、身体を起してアンジェリークの顔を見上げた。
アンジェリークと目があった。アンジェリークの翠緑の双眸は熱があるように濡れて潤んでいた。
オスカーはふ…と微笑むと両手を伸ばしてアンジェリークの頬を包みこみ、顔をはすかいにして口付けた。
上唇と下唇を交互に軽く吸ってから、そっと舌を差しいれた。
歯列をなぞり、歯茎と上顎をひとしきり舐ってからアンジェリークの舌に自分のそれを絡めて吸い上げた。
深い口付けでアンジェリークを酔わせつつオスカーはブラジャーの肩紐に手をかけてそれを腕のほうにずらしていく。丸い肩を愛撫するように優しくなでさすりながら。
同時に片手で器用に留め金をはずして、ブラジャーを完全に取り去ってしまった。
豊かにもりあがった形のいい乳房がふるりと揺れてオスカーの眼前に現れた。
「あ…」
アンジェリークは思わず唇を離して、声をあげた。乳房を隠したい衝動に身をよじる。
「お嬢ちゃん、そのまま、動かないで…今日はただ、そこに…」
オスカーが再度懇願するようにアンジェリークに囁いた。いつも情事では強引ともいえる態度をとりがちなオスカーが今日はあくまでアンジェリークの意志を尊重するような態度を見せる。
「このたわわに実った果実に感謝をこめて…」
オスカーはアンジェリークの乳房に手を添え、軽く揺らしてその重みを確かめてから、徐に先端に口付けた。
「あっ…ん…」
胸の先端から迸る電気が走るような感覚にアンジェリークは無意識に眉根をよせ、オスカーの腕を掴んで揺らぐ自分の体を支えようとする。
オスカーの唇が触れたとたんに乳首が固く立ちあがってしまったのが自分でもわかり、アンジェリークは羞恥に居たたまれない思いがわきあがる。
オスカーの唇を待ちかねていたように瞬時に反応を返してしまう自分の体がどうにも恥かしくて仕方なかった。
だがオスカーは嬉しそうにその立ちあがった乳首に舌を添わせて、乳首の下から上へと丁寧になめあげていく。
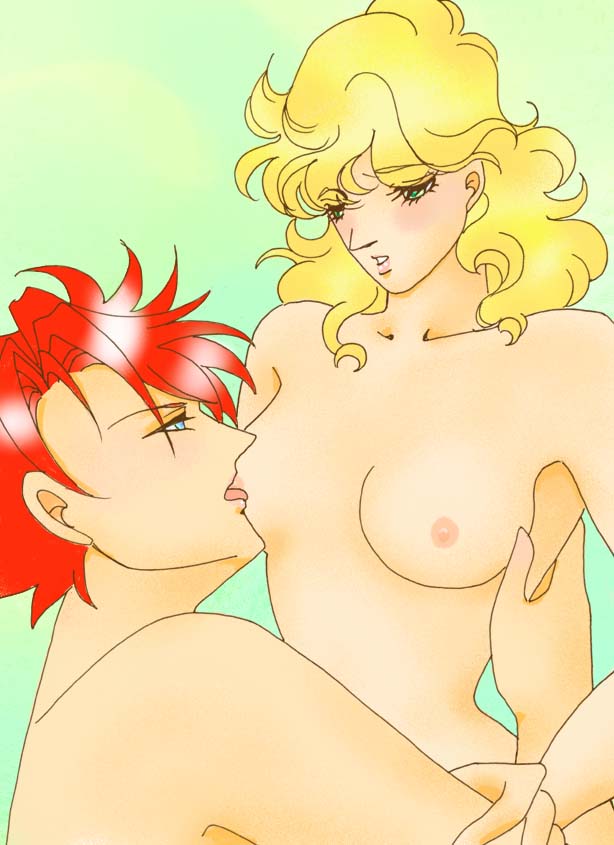
「この果実の優しさと豊かさに俺は感謝と崇拝の念をおさえることができない…どうか俺に心行くまで味わい尽くさせてくれ…」
オスカーは乳首全体に舌を這わせてから、先端をかすめるように小刻みに舌を動かした。
その触れるか触れないかの微妙な感触が、どうしようもない切なさを伴ってアンジェリークの身体を熱して行く。
「あっ…あん…あぁ…」
オスカーの舌が生き物のように、自分の胸の先端で踊り跳ねている。自分の乳首がオスカーの舌で弾かれ、つつかれ転がすように舐めまわされている。
『オスカー様の舌に私の…あんなにいろいろされて…すごく恥かしい…なのに、なんで、なんで私、見てるの?』
アンジェリークはその光景から目をそらすことができず、魅入られたようにオスカーの舌が自分の乳首を存分に舐るさまを見つめていた。
オスカーの舌に与えられる快楽が、自分の目で確かめることによってより鮮烈になるような気がした。
オスカーが一瞬顔をあげてアンジェリークを見た。
「お嬢ちゃん、自分の乳房が愛されているのを見てるのか?ふ…どんな気分だ?」
「あ…そんな…」
オスカーは乳房を自分のほうに突き出させるように揉みながら、ことさらゆっくりと乳首を舐りながら、重ねて訊ねた。
「さあ、正直に言ってご覧?俺に舐められているのをみてると、どんな気分になる?どうしてじっと見ていたんだ?言ってごらん、お嬢ちゃん。」
「いや、オスカーさま、いや…」
アンジェリークは力なく首を振る。
「言ってくれ、お嬢ちゃん、お嬢ちゃんの素直な気持ちが知りたい…」
オスカーが返答を促すように、アンジェリークの乳首にかりりと軽く歯をたてた。
「あっ…」
アンジェリークが軽くのけぞる。オスカーの二の腕にアンジェリークの細い指先が僅かに食いこんだ。
「さあ…」
諦めたように瞳を伏せ、アンジェリークは少しづつ言葉を捜す。
「んっ…あの、舐められてるって思うと、なんだか身体の奥がじんと熱くなって…その、おかしな気持ちになっちゃう…の…」
「いやらしい気持ちになるんだろう?そして、より感じちまう…違うか?」
「ああ…いや、言わないで…」
隠しておきたかった気持ちを指摘され、アンジェリークは思わず目を瞑って首を横に振った。
「お嬢ちゃん、目をあけて俺を見ろ。目を反らさず、瞑らず、俺がどうやってお嬢ちゃんを愛するか見るんだ。そして、もっともっと淫らになってくれ…それこそが、俺の望むことなのだから。」
オスカーの命令とも懇願ともとれる言葉にアンジェリークはゆっくりと瞳を見開いた。
オスカーの言葉はそれ自体に力があるが如くぐいぐいと胸に迫りくる。
オスカーの望むようになりたい。オスカーが淫らになれというのなら、いくらでもなれる、そんな被虐の喜びがアンジェリークを覆って行く。
「オスカーさま…見ます、オスカー様が私を愛してくれるところを…だから、もっと…もっと愛してください」
うわごとのような呟きを聞いて、オスカーはアンジェリークに一度口付けてから、
「ああ、俺はお嬢ちゃんを愛さずにはいられない、この奇跡のような幸せに感謝を奉げずにはいられない。これは俺の儀式なのだから…」
と言って再度乳首を口に含んだ。
「さあ、今、お嬢ちゃんのこのかわいらしい蕾はどうされてる?口にだして言ってご覧?言えるな?お嬢ちゃん…」
「ああ、オスカー様の舌に…」
「俺の舌にどうされているんだ?」
「下からも横からも舐められて……オスカー様の舌が生き物みたい…私の…ころがされてます…ああ、どんどん固くなっちゃう…あっ…先を…そんな風に舌先で細かくなめられると、すごく、すごく気持ちいいです…ああ…」
「ふ…どうだ?見ているままを言葉にすると余計におかしくなるだろう?こんなに固く尖らせて…さあ、今度はここを吸ってもいいか?」
固くそそり立った先端を指先で捻るように摘み上げながら、オスカーはアンジェリークを見上げる。
アンジェリークは自らの言葉に昂ぶり、瞳には紛れもない情欲の炎が揺らめいていた。
「オスカーさま…吸って…いっぱい吸ってください…」
「ああ、お嬢ちゃんのかわいらしい果実を存分に堪能させてもらう。」
オスカーはアンジェリークの乳房を根もとのほうから絞るように揉んでは、交互にその先端を音をたてて吸い上げた。
オスカーの唾液に塗れて艶々と濡れ光っていた乳首は、強く吸われた事で更に色濃く染まり文字通り熟した果実のような様を呈していく。
「ほら、こんなに色濃く熟して…俺に食べられて嬉しそうだぜ、お嬢ちゃんのここは…」
「ああ、オスカーさま…はい、嬉しいです。いっぱい食べてください…」
「その素直さがたまらなくかわいいぜ、お嬢ちゃん…」
オスカーはもう一度アンジェリークの胸元に顔を埋め、乳首を吸っては時折軽く歯をたてた。
「どれ…もうひとつの果実もそろそろ食べごろだろに熟した頃だろう…」
乳房への愛撫を続けながらそっと股間に手をさしのべショーツの奥に指をのばしてみた。
奥まで探らずともそっと触れただけで秘唇全体を濡らしてあまるほどに愛液が溢れかえっているのが指先に感じられた。
「ふ…こんなに滴らせて…この果汁も俺に味わってほしくてこんなに溢れているのか?」
ショーツの中で指を蠢かしくちゅくちゅとわざと水音を響かせてオスカーはふっくらとした秘唇をやわらかくさする。
「ああっ…」
オスカーの腕を掴んで懸命に上体を支えようとしていたアンジェリークが、たまらない様子でオスカーの首に両手をかけなおし身体ごとオスカーのほうに投げ出してきた
「ああ、オスカーさま、オスカーさま、私、私…」
「わかってる、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんのいいたいことはな…」
オスカーはアンジェリークの膝をたたせるように両手で抱えあげてから、そっと下着を脱がせた。
そしてあらわになった秘唇の合わせ目にそろえた指先をつぷりと僅かに差しいれ入り口の部分をゆっくりとほぐすように掻き回した。
「お嬢ちゃん、俺にここも愛してもらいたいか?」
「あ……オスカーさま…そんな…恥かしい…でも…」
「でも?なんだ?さあ、お嬢ちゃん、どっちだ?愛してもらいたいか?そうでないのか…」
指を少しだけ合わせ目にもぐらせ、焦らす様に上下にゆっくりと動かしながらオスカーはアンジェリークの心と身体に火をつけていく。
身も心も灼く炎がどうにも鎮められなくなるまで、オスカーはアンジェリークを追い込んで行くつもりだった。
「あ…愛してください…オスカーさま…オスカー様に愛していただきたいです…」
アンジェリークはあっさりと心を明け渡した。自分の口から愛撫をねだることで、より激しく熱い昂ぶりが身中に沸き起こり己の身を焦がす。
オスカーはそれをわかっていて、自分に羞恥を煽るようなことをわざと言わせようとするのだということを、もうアンジェリークは知っている。こんな恥かしいことを言わせるのも、自分により深い悦楽を与えたいがため。オスカーのその気持ちがわかるから、アンジェリークはオスカーの命に素直すぎるほどに従ってしまう。
オスカーが背筋を伸ばしてアンジェリークに口付けた。これは褒賞のキスなのだとアンジェリークは感じている。
「俺はお嬢ちゃんの望むようにしてやりたいんだ。だが、俺自身もお嬢ちゃんの溢れる泉で唇を潤したい…なにより俺を酔わせるこの美酒で…だから、俺は謝意をささげる。その許しを与えてくれたことに…そしてこのどこまでも豊穣な肉体に…」
オスカーはアンジェリークの足を自分の肩に担ぎ上げた。
「あんっ」
アンジェリークはその反動で僅かにのけぞりベッドに腕をついて身体を支える。
秘唇は完全にオスカーの眼前に晒されていた。
「ああ、オスカーさま…こんな、こんな格好恥かしい…」
「なにも恥ずかしがることはない。この美しい花を俺はつぶさに見つめて…そして称えたいんだ。」
自由になった両手で、オスカーはアンジェリークの秘唇をぐっと押し開いた。そのまま幾重にも重なった花弁を一枚一枚丁寧に指でなぞる。
「ほら、豊かに溢れる露を湛えてお嬢ちゃんの花はなにかを待つように咲き綻んでいる…こんなに赤々と染まって…」
「ああ…いや…みないで…」
「お嬢ちゃんの花が待っているのはこれか?」
伸ばした中指をそろりと花弁の中心にオスカーは飲み込ませて行く。反射的に締め付けてくる肉壁に逆らう様に指を進めると奥では逆に蕩けるような肉襞がやわやわとまつわりついてきた。
その柔襞を刺激するように、指を軽くまげてかきまわす。
その瞬間アンジェリークの身体に細かい震えが走った。
「は…ああ…」
「お嬢ちゃんの花はこれだけでは物足りなさそうだな…ああ、そうだ…」
オスカーは指を回しながら、もう片方の手で秘唇の上部を思いきり広げて隠れていた花芽を露出させた。
「花の上にもかわいい実があったな…艶々と輝いている…きれいだな…」
オスカーはそういうと、親指と中指で秘唇をひろげたまま、花芽を人差し指でそっと転がした。
「あああっ!」
それでなくても敏感な花芽を直接弄られアンジェリークは高い声を放った。
「お嬢ちゃん、この実もみるからに美味そうに熟しているが、ここも俺に食べて欲しいのかな?」
オスカーは指の腹で花芽を円を描く様になでさすりながらアンジェリークに問いかける。
「さあ、俺の唇で触れてほしかったらそう言うんだ、お嬢ちゃん…」
重ねて請われるほどにアンジェリークの理性は麻痺して行く。心を焼く羞恥があるからこそ、より悦楽も深くなることをしっている、いや、教えこまされたアンジェリークはもう悦楽への期待に逆らえない。
「はい、オスカー様…唇で…オスカー様の舌で愛してください…いっぱい食べてください…」
「なら、お嬢ちゃん、それをちゃんと見るんだ。俺がどうやってお嬢ちゃんを愛するのか。お嬢ちゃんはどんなことを俺に望み、それを叶えてもらうのか、その目で確かめるんだ。いいな?」
オスカーに言われなくてもアンジェリークは目をそらせなかった。
オスカーの唇が剥き出しになった花芽に近づいていく。
オスカーが舌をみせつけるように差し出す。高まる期待に胸がはちきれそうになる。
舌の先端がそっと花芽に触れる。とたんに脳裏に鋭い稲妻が走った。
「あっ…」
アンジェリークの声が合図になったように、オスカーの舌が素早く小刻みに動いて花芽を縦横に舐り始めた。
同時に、ゆっくりと肉壁を掻き回していた指も、奥を狙うように激しい勢いで突き入れられてはひきぬかれた。
「あっ…ああっ…やぁっ…そ、そんな急に激しく…」
「だが、これがたまらないんだろう?お嬢ちゃんのここはこんなにびくびくと蠢いて…ほら、この果実もこんなに固く膨らんで…」
「ひぅんっ!」
オスカーが花芽を口に含んで強く吸い上げた。
その拍子に指がきゅっと締め付けられた。
アンジェリークの愛液は止め処もなく溢れ、オスカーの手首まで濡らしている。
オスカー自身がもうこらえ切れなくなったように擦れた声でアンジェリークに懇願した。
「お嬢ちゃんの蜜を味あわせてくれ…」
オスカーは指をひき抜くと替りに尖らせた舌を秘裂に差しいれながら、秘唇全体を強く吸った。
オスカーは喉をならすようにアンジェリークの愛液を貪った。
「はぁっ…」
アンジェリークはもうオスカーが自分の股間で何をしているか見る余裕などとっくになかった。
自分の身体を支えている手はぶるぶると震えて今にも崩れ落ちそうだった。
「オスカーさま、だめ!私、もう…」
「もう、どうしたいんだ?お嬢ちゃん…」
オスカーの自分のすべてを食らいつくそうとせんばかりの激しい口戯に、心は白い闇に染まっていく。
吸い尽くされ貪られることで生じた飢えは極限に達していた。自分の欠けた部分を埋めてもらう事しか考えられなくなっていた。
「あっ…お願い…オスカーさま…もう、もうきて!私をいっぱいに充たして!」
「それがお嬢ちゃんの願いなら…」
オスカーは立ちあがると、アンジェリークの足首を掴んで大きく股間をひらかせた。
アンジェリークの身体は安堵したように自然とベッドに横たわった。
オスカーは自分は立ったまま、今まで口で愛していたその部分を猛り切った雄渾のもので一気に貫いた。
「あああっ…」
アンジェリークの背が大きくそりかえった。
ゆっくりとひきぬいてから、オスカーはリズミカルにアンジェリークに自分の肉楔を打ち込みはじめた。
しかし、最奥まではつき入れずに秘裂の中程まで突き刺してはひき抜くことを繰り返している。
アンジェリークが焦れたように腰をくねらせはじめた。
「や…オスカーさま…もっと…もっと…」
「もっとどうしてほしいんだ?」
「奥まで、奥までいっぱい下さい、思いっきり突いて!オスカーさまぁ!」
「ふ…そんなに欲しいのか?」
「欲しいの、オスカー様のが欲しいの!お願い、意地悪しないで!」
「俺がお嬢ちゃんに意地悪なんかするわけないだろう?お嬢ちゃん、なら、存分に味わってくれ、そら!」
言葉と同時にオスカーが渾身の力をこめて腰を叩きつけた。
そのまま最奥を抉るような激しい律動をこれでもかとばかりに繰り返し始めた。
「はぁああっ…」
アンジェリークは激しくかぶりを振った。
金色の髪が白いシーツの上に散らばる。
細い指はなにか掴まるものを求めるかのようにベッドの上をさ迷う。
「ああっ…オスカーさま…すごい、すごいの…」
「俺も…すごくいいぜ…お嬢ちゃんは最高だ…」
「オスカー様っ、もっと、もっと来て!オスカー様を思いっきり感じさせて!」
「くっ…」
オスカーはアンジェリークの足を両腕に抱える様にしてからアンジェリークに覆い被さり、アンジェリークの身体をくの字に折り曲げるような姿勢できつく抱きしめながら、さらに強く肉楔を打ちこんだ。
アンジェリークが無意識にすがるようにオスカーの肩に腕をまわしてきた。
「ああああっ…だめっ…もうだめぇっ」
「お嬢ちゃん…好きだ…好きで大事でたまらないんだ…」
「オスカー様、私も、私も…あっ…はぁあっ…」
オスカーの肩にアンジェリークの指が瞬間食いこんだ。
オスカーはその機を逃さず、体重をかけるような激しい一撃を深深と打ちこんだ。
「あああああっ!」
アンジェリークの秘裂がびくびくと激しい収縮を起すと同時にオスカーも自分の欲望のすべてをアンジェリークの最奥に放った。
オスカーは力を出し切った様にアンジェリークの上にゆっくりと突っ伏した。
この程度で体力を使いきる訳はないのだが、なぜだかアンジェリークに自分の身体を預けてみたくなった。
アンジェリークの美しい乳房の谷間に顔を埋める。乳房、いや身体全体がほんのりと霧を吹いた様に汗でしっとり潤んでいた。
アンジェリークは嫌がる素振りも見せず、オスカーの背中をきゅっと抱きしめてから燃え立つ髪の毛を指で梳くようにオスカーの頭をなでる仕草を繰り返した。
激しい情事の後、とてつもなく優しい気持ちになれる時間。この時間がオスカーはとても好きだった。
そしてこんな豊かな時間があることを自分に教えてくれたアンジェリークにオスカーは感謝する。崇拝せずにいられないと思う。
気負うことなく感謝を示す言葉がするりと口から出た。
「お嬢ちゃん…ありがとう…お嬢ちゃんは俺の女神だ…豊穣の象徴なんだ…俺のわがままもなにもいつもすべて受け入れてくれる…」
「オスカー様…そんな、かいかぶりすぎです…私はオスカー様のことが好きなただの女です…」
「いや、ただあるがままに受け入れてくれる…俺の欠点もどうしようもないところも、今まで生きるうちに否応なく沁みついてしまった澱のようなものすらも、お嬢ちゃんはそのまま受け入れてくれる。限りない豊かさで…そして、俺は君の中に知らなかった自分を見つけるんだ…お嬢ちゃんが俺のすべてを受け入れてくれるからこそ見つけられるんだ…俺はそう思っている…」
「そんな、そんなことないです…ただ、オスカー様がオスカー様だっていうだけで、私はオスカー様が好きです。それだけです…」
それは簡単そうでとても難しいことだ…オスカーはわかっている。なんの利害や損得もなしに、人を好きになりその人間のあるがままを受け入れる事は…だから、君は俺の女神なんだ、ありとあらゆる癒しと許しを与えてくれる。でも、君はそう言っても納得はしないんだろうな…
「それが嬉しいんだ、俺は…」
オスカーは改めてアンジェリークに長々と口付けた。
唇を離してアンジェリークの頬に手を添え、瞳を細めていたわるように言葉をかけた。
「すまなかったな。無理やり急かしたのにパレードが全部は見られなくなっちまって…」
「いえ、そんな、オスカー様のお気持ちが嬉しかったですから…」
アンジェリークがここまで言葉を発した時窓の外が一瞬ぱぁっと明るくなり、その直後、腹の底に響くような重々しい爆発音が聞こえた。
「なんだ?今の音は」
オスカーは思わず窓の方を見た。
「あ!もしかしたら!」
アンジェリークはぱっとベッドから飛び起きて窓の側にかけよりさっとカーテンを開いた。
「こ、こらお嬢ちゃん!そんな格好でカーテンをあけちゃだめだ〜!」
オスカーは慌てて下着だけ身に付けると、ベッドの上掛けを引っつかんでアンジェリークのもとにかけより華奢な身体を白い布で覆い隠した。
「あっ!きゃー!ごめんなさい、オスカー様!ありがとうございます。」
胸元で布を手繰り寄せてアンジェリークが頬を染めた。
「まったく恥かしがり屋のくせに、妙なところで大胆だな、お嬢ちゃんは…ベッドの中と同じだな?」
アンジェリークの頬にちゅっと口付けながらオスカーが囁きかける。
「いやん、言わないで、オスカーさま…」
耳まで真っ赤になってアンジェリークが自分の頬を押さえた。
「お嬢ちゃんの綺麗な身体をみせるのは俺だけにしてくれよ?もったいないからな。しかし、なにをそんなに慌ててたんだ?」
「あ、ほら、オスカーさま、見て」
アンジェリークが指差した空がまたぱぁっと光った。手が届きそうなほど近くに大輪の花火が開いていた。
そのまま立て続けに花火が幾重にも重なっては開き消えて行く。身体を震わすほどの音が後を追って聞こえてきた。
二人とも黙って夜空に咲く光の饗宴を見つめていた。
「花火の打ち上げもあったのか…最初の音は始まりの合図か…」
ほぅと小さく吐息を漏らしてからアンジェリークが答えた。
「ええ、昔もそうでした。忘れてましたけど、パレードのあとは花火があったのを、さっきの音で思い出したんです。それで慌てちゃって…子どものときに見たことありましたけど、こんなに近くから見たことはなかったです。ここ、すっごくいい場所だったんですねぇ」
「ああ、通りから一本はずれたホテルだったのに妙に混んでいて空きがなかったのは花火見物に絶好のロケーションだったせいか…」
「あ、また始まりましたよ」
アンジェリークに促されて目をやるとまた大玉・小玉・しだれといろいろな花火が立て続けに空を彩り始めた。
アンジェリークがオスカーの胸に頭をことんともたせかけた。
「オスカーさま、ありがとうございます。今夜ここにつれてきてくださって…」
「いや、偶然だから、礼を言われることじゃない。」
「でも、オスカー様がつれてきてくださらなかったら、見られませんでした。だから…」
「まあ、結果オーライだがお嬢ちゃんが喜んでくれたなら、俺もいうことはないな。お嬢ちゃんが幸せなら、俺も幸せだからな。」
『私はオスカー様が嬉しい気持ちでいてくださることが一番の幸せなんですよ…』
アンジェリークはこんなことを心の中で思いながらオスカーの顔をみあげた。
オスカーが柔らかく微笑みながらアンジェリークの頤をつまみあげる。
アンジェリークは間もなく触れるであろう唇の感触を思って瞳を閉じた。
色とりどりに咲き乱れる光の洪水を背に別ち難いシルエットが浮かびあがった。
FIN