アンジェリークはオスカーに言われた通り目をあけていた…互いを見つめいながらの口付けも別にきまずくはない。むしろ夢に捕らわれて中空を漂っているような非現実感がアンジェリークの心を軽やかにしていた。
オスカーの瞳を追うように見つめていると酩酊感にくらくらしてくるが、それがむしろ心地良い。呪文のように繰り返される低い穏やかな呼びかけもその酩酊感を助長しているのかもしれない…
あれと同じ声のはずだった…一瞬でもそう思ったのが申し訳ないほど、オスカー自身の声は深みがあり、落ち付いていて、それでいて、時折背筋にぞくりと戦慄が走るほどに蠱惑的だった。低く抑えた声音で唱えられる自分の名には思いやりと労りが満ち満ちていた。人の品性とか本質というものは声に如実に現われるのかもしれない。美声かどうかではなく…抑揚や話し方という全体の印象に…
話し方が全く違うとはっきりわかるから、自分へ語りかける声はやさしさが滲み出ているのがわかるから、アンジェリークは混乱しないし、今進みつつある行為を思っても恐慌状態にもならずに済んでいる。それがわかっているからか、オスカーはゆっくりと静かに、口付けの間に間に途切れることなく、アンジェリークの名前を呼ぶ、呼び続けている。
繰り返される名前は確かに呪文のようで、自分の心中を安寧で満たし、浮き立ちそうになる心を鎮めてくれている。
甘い、それでいてしっかりとした声でよびかけられていると、確かにここにいるのは、オスカーその人なのだと心の奥深い部分で感じ取れ、それがアンジェリークの気持ちを落ち付かせてくれる。
触れては離れるだけだった唇が、少しづつ能動的になってくる。上唇と下唇を交互に軽く食むように動く、軽く吸う、角度を変えてまた触れる。
オスカーの腕は包むようにゆったりとアンジェリークを抱いたまま、髪の毛から背中を飽くことなく撫でさすっている。アンジェリークを抱く腕は力強さを感じさせながら、限りなく優しい。
オスカーの優しさに、私はこんなに甘えてしまって、いいのだろうか…
いいわけがない。理性はそう語りかけてくる。アンジェリークは自分が恋する女のエゴを押し通してしまった自覚を十分に持っていたから。
結局、オスカーに抱いてくれと頼んだのは…誰のためでもない、ジュリアスをこれ以上苦しめることに耐えられない、その思いからだった。それだけだったと言ってもいい。
ジュリアスに承知の上で辛い選択をさせるくらいなら…ジュリアスになにも知らせずに済むほうがまだいいと思ったのだ。あの人の知らないところで、私がオスカーを偽者と混同して動転しなくなれば、あの人も私を心配して心を痛めなくなる…
自分自身を幽閉することは、結局ジュリアスの懊悩を増すことはあっても減じることはないのではないかとアンジェリークにはどうしても思えてしまう。
この選択はオスカーたちの身を守り女王としての義務を果すことはできても、愛する人の心を哀しみで曇らせてしまう。真実を告げても告げなくてもそれは同じこと。なにも言わないで宮殿の奥深くに閉じこもったら、あの人に『自分は信頼されていないのか、見切られたのか』と悩ませ傷つける。理由を打明ければあの人はきっと、私が閉じこもらずに済む方策はないか、懸命に考えてしまうと思う。自分のためじゃない。私のために、聖地のために…そして、もしこの方法に気付いたら…オスカーが気付いたのだもの、オスカーに仄めかされて私も気付いたのだもの、ジュリアスが気づかないという保証はないのだもの…自分が苦しくても、身を切られるほどに辛くてもオスカーに私と寝てやってくれと頼んでしまうかもしれない。
それなら…どちらにしろ彼を苦しめてしまうなら…彼にはなにも知らせないところで、私が…オスカー、あなたに怯えずに済むようにできれば…それが1番いいような気がしたの…馬鹿なことかもしれない。結局彼を裏切っているのかもしれない…でも、彼が苦しむのを見たくないの、彼をもう苦しめたくないの…女王としての義務は果さなくてはならない、でも愛する人を哀しませたくもない…結局私が考えたことはこういうこと…あなたに抱かれることで自分の理不尽な恐怖を宥めることができれば…今まで通りの治世が行える。そうすればジュリアスを悩ませる事なしに女王としての義務も果していける…そんな手前勝手なことを考えて、あなたに、抱いてくれとお願いに来たのだもの、私は…
流石にそれをオスカーに告げて理解を求めるほど、虫のいいことはしなかった…
だって、オスカーには何の義理も義務もないことなのだから。ジュリアスが苦しむ所をみたくない、という私の願いをかなえる義理なんて、オスカーには何もないのだから。
オスカーが私を助けてくれるのは、私が自分を幽閉しないですむように。それを純粋に不憫に思ってくれたから。オスカーは優しい…だからと言って忘れてはいけない。私のエゴを充たすためにオスカーは私を助けるのではないということを。
この選択の動機はどこをどう取っても自分のエゴだった。しかも恋する女の近視眼的なエゴだと思った。でも…ジュリアスに言われてみて気付いた。自分が最も強く願う事…それは…ジュリアスに憂いを抱いてほしくない。ジュリアスには心安らかでいてほしい。笑ってくれていればもっと嬉しい。そういうことだった。ジュリアスが自分に『笑っていて欲しい、そのためならどんなことでもしよう』と言ったように、自分の望みも、つきつめて言えば『ジュリアスに笑っていて欲しい』それだけだった。ジュリアスの側に自分がいられるかいられないかは極論すればどうでもよかった。
本当は…誰かを苦しめないで…ううん、ジュリアスが苦しまないですむのなら、自分が幽閉されても、2度とジュリアスと会えなくてもいいと思った。むしろ、喜んでそうしたと思う。
でも、ジュリアスは…それは哀しく寂しいことだと言っていた。
だから…馬鹿なことかもしれないと思った、ジュリアスへの裏切りかもしれないとも思った、それでも、自分を幽閉しないで済む可能性を試してみたかった。
前女王陛下の選択の方が、女性としては潔いのだろう。
でも…とアンジェリークはふと思う、それはクラヴィスも望んだことだったのかしら…と。
クラヴィスは本当はどうだったのかしら…添い遂げられない人の姿を…目の前にいるのに触れることができないほうが辛かったのかしら…それくらいなら、会わずにいるほうが辛くなかったのかしら…陛下が宮殿の奥深くにいることの方がクラヴィス自身にも救いだったのかしら…
前陛下は…クラヴィスがより辛くないほう…少しでも耐えやすい方法だと思って隠遁されたのかしら…そう思いたい…実際にそうであってほしい。それでもクラヴィスは寂しそうな時が多かったもの…そうでないと…2人とも辛い思いをしたのに、2人供に報われない…
相手のためにと思って選んだ選択がより相手を苦しめてしまうこともある。それがわかっているから私は選択するのが怖かった。オスカーの提案を受け入れるか、受け入れずに自分を幽閉するのか、自分がよかれと思った選択がジュリアスをよけいに苦しめてしまうことが怖かったのよ。
恐らく異世界の女性が選んだ自死という結末も、皇帝を苦しめるとも思わず、それが皇帝にとって一番いいことだと彼女が思いこんでしまったからだろうし。その一人よがりな「相手のため」が愛する人を完膚なきまでにうちのめしてしまうこともあるのだと、今の私は知っているから。
そして私の選んだこの選択は…真実を知ればジュリアスがやっぱり傷つき苦しむ選択だと思う。ジュリアスはそれを仕方ないと思うかもしれないが、だからといって葛藤しない訳がないと思う。だから、私は絶対にこのことをジュリアスに…微塵たりともジュリアスに気付かせてはいけない。そんなことをしたら、自分の最も強い願い…彼を苦しませたくないという願いを自ら裏切ってしまうことになるから。いつか…いつか私が聖地を去るその日まで自分一人の胸に…ううん、本当はオスカーと2人でなのだろうけど…ずっと抱え続けてみせる。
私が何も言わずとも、オスカーならこの事を2人だけの胸の内に収めてくれることも、それを外に出さないでくれるだろうことも、理屈でなく信じられる。そう、この人ほど信じるに足る男性はいない。
そう思いオスカーを見つめた。
オスカーはアンジェリークの事をなぜか寂しさを感じさせる瞳で見つめ返しながら、羽毛で触れるような口付けを繰りかえしている。その優しく寂しげな瞳の色を見て…オスカーの瞳の淡い青色が涙の色のようだと不意に思え、アンジェリークはオスカーに思いきり謝罪したい衝動に激しく揺さぶられた。
オスカー、オスカー、ごめんなさい、私のわがままにまきこんでしまって…でも、ありがとう…助けてくれて…私を助けようとしてくれて…
そう思うと心の内側にほんのりと火が灯る。オスカーの点けてくれた炎が自分を暖めてくれるのを感じる。
そうだわ、私にはオスカーがいてくれる…一人じゃなかった…一人で選んだことじゃなかった…オスカーが一緒だから、私は勇気を出せたんだわ。オスカーが一緒にいてくれるから、この選択が一人よがりではないのかも…と思うこともできるんだわ…
私、オスカーが…言ってくれたのがオスカーだから、賭けて見る気になったのだと思う。オスカーなら信じられるから。オスカーなら何もかも信じられるって思ったから。他のひとが相手だったら…やっぱり断っていたと思うの。オスカーだから大丈夫だと感じたのだと思うの。
そのせいなのかな…私、今オスカーの口付けも抱擁も怖くない。嫌じゃない。自分でも不思議…
そう思っているのは本当なのに、アンジェリークは自分がいまだ自分自身を守ろうとするように頑なに手を胸の前でぎゅっと組んでいることに気付き、その力を緩めた。
組んでいた指を解いて自然に腕を降ろした。肩の力が抜けたのが自分でもわかった。すると、オスカーが自分を抱きしめる力が少しだけ強くなった。ほんの少しだけ厚い胸板に押しつけられるようになった。触れあう面積が広くなった。
『わかってくれてる…オスカーは…私の頑なさを…いまだ尻ごみ躊躇っている心をわかってくれてる…』
だから、必要以上に触れてこない。自分の態度が軟らかくなった分だけ触れてくる。でも、強引じゃない。当然って態度じゃない。私がどこまでなら平気なのか入りこめる部分を探るように、距離を測りながら近づいてきてくれてる…私が退こうとしたら、自分もすぐ退けるように…そう思ってくれてるのかもしれない…
大丈夫、オスカー…こんなに優しくしてくれるから…私、きっと大丈夫…
お願い、オスカー…あなたが私の名前を呼ばない時でも、どんな時でも、あなたはあなたなんだって、ここにいるのはオスカーなんだって、私にもっと強く信じさせて、どうか、一欠片の迷いも入りこむ隙間のないように…
おずおずと、相手の出方を探るようにアンジェリークは自分から腕を上げた。そして、躊躇いながらもその腕をオスカーの背に回した。
その瞬間オスカーは体に電撃が走ったような気がした。その激しく重い衝撃にオスカーはしばし呆然としたほどだった。アンジェリークの小さな掌の感触の意味を感じ…自分への信頼を懸命に現してくれようとしているアンジェリークの思いに涙が出そうだった。
タイミングを見誤ってはいけない。彼女の必死の勇気を汲んで、応えないと…彼女はまた竦んでしまう。振り絞った勇気を後悔してしまう。
オスカーはアンジェリークの背中に回した手にぐっと力をこめた。
一度口付けを解き、静かに、しかしあきらかに力を込めて囁いた。心の準備を促すように。
「アンジェリーク…」
間髪いれずに再び口付けた。同時に綺麗に揃えられた足の下に腕を回して、アンジェリークを軽々と持ち上げた。
アンジェリークの体がオスカーの腕のなかで瞬間硬化した。だが抗いはしなかった。僅かでもオスカーの体を退けようとする気配はなかった。
「あ…オスカー…」
「…怖いか?」
アンジェリークの瞳を気遣わしげに覗きこみ、唇と、頬と、額と…交互に口付けながらオスカーが尋ねた。
「…ううん、ちょっと驚いただけ…」
はにかんだように俯いたその髪の毛にオスカーはそっと頬ずりをした。
「怖いことはしない。だが、少しでも嫌な時は…すぐ言ってくれ…どんなことも我慢しないで…」
「ん…」
狭い部屋でよかったとオスカーは思った。迷い出す前に…彼女だけじゃない、自分もだ…アンジェリークをベッドに運ぶことができる…そう思ったから。
簡素なベッドである。ヘッドボードに装飾の一彫もない。仮宮とはいえ宮殿の客間の調度だから清潔に保たれ寝心地もいいが外見は愛想も素っ気もない実用一点張りの寝台だった。そして自分たちのこの情事には…あくまで愛の営みではない、愛の営みと思わせてはならないこの情事にはこんな実用性を強調したベッドこそ相応しいとオスカーは思った。甘い口説は…どれほど切切と訴えたくてもそれが今は一切無用なのと同じだ。
オスカーはアンジェリークの体をそっとベッドに置いて腰掛けさせ、自分もその脇に座り改めてアンジェリークの体を軟らかく抱き寄せた。
まだ横たえるのは早い…理性がそう告げていた。彼女の緊張がもっと解けるまで。彼女がもっと自分をうけいれる気持ちになってくれるまで。
今夜一晩時間をかけても結局彼女は俺の全てを受け入れられないかもしれない。
それはそれで仕方ないと思うし、当たり前だが、結果を急ぐ気や無理強いする気など寸分もない。彼女は俺を信頼して、俺の提示した方法に自分を預けてくれた。それだけで自分は報われているし、俺の抱擁と口付けは受け入れてくれた…これだけでも絶対にいい効果は望めると思う。完璧に情交することが目的ではないのだから、それを忘れないようにしなければ…
そう思いながら肩を抱き、再び口付けを始めた。手はゆっくりと、だが1ヶ所に留まることなくまろやかな肩を、頬を、首筋を、そっと撫でさする。自分の指先で彼女の体の固さを解いてやりたいと思う。
唇を寄せる。触れる。鋏みこむ。軽く吸う。アンジェリークの甘く芳しい唇は触れても触れても物足りない気がする。もっと深く…触れたい、今触れているだけではとても足りない、渇いていて、潤してほしくてもっと深く繋がりたくて…
オスカーは触れ合えば触れ合うほどにどうしようもなくアンジェリークを恋し愛してしまっている自分を嫌というほど思い知る。
近づきたい、触れたいと思う気持ちこそが恋で、恋しているからこそ俺は彼女ともっと深く…人間の根源の部分で触れ合い繋がりたいと際限なく思ってしまう。それが人が人を請い求める気持ちだから。だから肌を触れあわせひとつに繋がりたいと人は思うのだから。
俺はやはり彼女に触れたいと思う気持ち、できる限り深く繋がりたいと思う気持ちを抹消することはできない。彼女を愛する気持ちをどうしても消せなかったように。
でも、だからといって俺は自分を責めない。彼女もまた俺との繋がりを求めてくれたのは確かだから。動機は問題ではない。それに俺は、彼女の求めるものを与えられるのが俺であって嬉しい。それが誰でもない俺であることが、やはり嬉しいんだ。こうして彼女に求められ、求められたものを与えられるかもしれないのだから。彼女が幸せになる手助けをしてやれると思うことが震えるほどの喜びなんだ。そう思えるようになったから、もう彼女を抱くことを躊躇わない。罪悪感も持たない。
アンジェリーク、どうか、感じてほしい。心をこめた…真摯な心を伴った触れ合いしか、俺は為さないと。心の伴った触れ合いならば、それはつまり俺・オスカーの行為なのだと。
見た目は似ていても自分勝手な欲望の押しつけは情事などではない。単なる理不尽な暴力だ。彼女が苦しんでいるのはその暴力の残した傷の痛み、その傷を与えたものが俺と同じ容姿だったから、俺がまた同じ暴力を振るうのではないかと言う理屈ではない怯え。
だから、俺は魂の全てもって証明する。俺は、君に愛しさしか覚えない、君に喜びと安らぎしか与えない。君の目の前にいる男はどんな時であれ、君を苦しめる事はないと身をもってわかってもらいたい。
この思いが伝わらんことを願って、彼女を抱きよせ、柔らかく撫で、そして口付ける。
ふと見ればアンジェリークはまだショールを肩にかけたままだった。オスカーは触れる口付けを繰り返しながら、そのショールをそっと取り去った。次の瞬間オスカーは大きく目を見張った。
アンジェリークはその下に夜着しか身に着けていなかった。オスカーは心底驚いたもののその姿に思わず心奪われた。
艶やかなアイボリーのシルクでできたそれは夢のような触り心地で、てろんとした素材ゆえ彼女の体に綺麗に沿ってその美しいなよやかなラインをより強調している。レースやフリルは襟と裾に少々あるだけで決して華美でもこれみよがしにセクシーでもないが子供じみてもいない。けぶるような真珠色の光沢もあくまで上品な輝きだ。
しかし、どれほど上品で美しくても夜着は夜着だった。アンジェリークが体を覆い隠すようにショールをきゅっと引き絞っていたのも漸く合点がいった。
その意味を見誤るオスカーではない。
アンジェリークの決意というか誠意というか…そう、十重二十重に着込んでいたら、それを脱がすまでに彼女自身が怖気ついてしまうかもしれない。本当は乗り気でないと思わせてしまうかもしれない。もったいぶった駆け引きもする気はない…尤もそんな考え自体彼女にはないかもしれないが…とにかくアンジェリークは自分の決意を表すために思いきって夜着で自分を訪れたのだと思った。
オスカーはその艶やかな布の感触を楽しみながら、アンジェリークの背中をそっと抱いた。少しだけ力をいれて自分の胸元に抱き寄せた。彼女の体が布越しに自分の胸板に押しつけられ…柔らかな感触が自分の硬質な胸に押しつけられてつぶれているのを感じた。
オスカーの神経は彼女と触れ合っている胸の部分に集中してしまう。胸の部分に下着の感触が感じられなかった。
彼女の本気がひしひしと伝わってきた。
しかし、そう思うだけでオスカーの頭は沸騰しそうだった。俺は本当に最後まで自制できるのか、あくまで彼女本位に動けるのか…俄かに自信が萎んでいく気がした。
それでもオスカーはアンジェリークの夜着のボタンに手をかけ、それを一つづつ外して行った。彼女の誠意の前に自分が怖気づいてどうするのだと言聞かせながら。
その間も口付けを繰り返す。まだ舌は差し入れていない。でも、唇を食んでも吸ってもアンジェリークは嫌がる素振りを見せないでくれた。
その事実に押されるようにボタンを3つまで外して、白い胸の谷間の蒼白い陰影が微かに覗いた時、一度オスカーは口付けを解いてアンジェリークの瞳を問い掛けるようにみつめた。
アンジェリークは震えながら微かに頷いた。
オスカーは思いきったように自分の黒のアンダーをまず毟り取るように脱ぎ去った。鞭のようにしなやかで無駄のない肉体が現われる。それからもう一度アンジェリークに口付けながら夜着のボタンを全部外した。
彼女が竦んでしまうほどの考える時間を与えるのはかえって残酷なような気がした。
彼女の立場ならまだ迷いが出ても当然なのだから。もちろんオスカーはあくまでアンジェリークの願いを優先させるつもりである。彼女が嫌だといえば、決してそれ以上に進む気はない。
だが彼女は静かにであっても、きちんと決心しているようだった。
その振り絞った勇気の末の決意を自分の優柔不断な態度でぐらつかせてはいけないような気がした。
それでも…夜着から腕を抜くのはオスカー自身にも大層勇気の要ることだった。だが、彼女は抗わないでくれた。そしてその下から真っ白な肉体が現われた時、オスカーは息を飲んだ。その瞬間時間が止まったような気がした。魂を奪われたように見入ってしまった。そして、オスカーは彼女のサクリアの発現である白金色の翼ほどに美しいものなどこの世にないと思っていたことが間違いだったと知った。
彼女の体のあまりの美しさに息が止まる思いだった。不躾に見つめてはいけないと思いながらも、オスカーはどうしても目をそらせない。
乳白色の肌は肌理こまかく透き通るようだ。ふっくらとした乳房は大ぶりではないが形がよく綺麗なラインが挑発的だが、桜色に染まる先端は可憐で愛らしく、愛撫を待っているような風情がなんともいじらしかった。綺麗なS字を描くウェストは自分の両手で掴みきれてしまいそうに括れている。なだらかですべすべとした腹部は白いレースのショーツに覆われているが、うっすらと金色のあわいが透けて見える様は悩ましいというよりは、なぜかかわいらしく感じらた。微妙な捻りをみせる腰のラインからはすんなりとした綺麗な足が伸びている。柔らかな曲線のみで構成された、やさしげでなよやかに美しい体だった。
だが…自分でも不思議な事に心を灼く情欲には悩まされなかった。抑えがきかなかったら、もし、いきなり彼女を組み敷いてしまったら…という不安は忘れ去られていた。
ただ、賛嘆の思いをこめて見つめずにはいられなかった。
服を取り去るために僅かに体を離したので、アンジェリークもオスカーが自分をまじまじと見つめていることに気付き、思わず胸を両手で覆った。
「や…そんなに見ないで…」
「…すまない…あまりに君が綺麗だから…見つめずにはいられなかった…」
「うそ!私、綺麗なんかじゃない!オスカー、オスカーは知っているのに…だから、お願い、暗くして…見られたくないの…」
手負いの動物が傷に触れられたかのような激烈な反応だった。オスカーは、しかし、あくまで沈着な声で感じたままをアンジェリークに告げる。自分の言葉はまったき真実なのだから、わざとらしい抑揚や強調など不要だから。
「君がそうしてほしいなら、灯りは絞るが…だが、俺は嘘はつかない。君は本当に綺麗だ、君みたいに綺麗な体をみたことがない…俺は真剣に見惚れていたんだ…」
「うそ…」
今度のアンジェリークの抗弁は力ない。
「俺の言うことは信じられないか?」
非難するようにではなく、あくまで優しくあやすようにオスカーは問うた。
はっとしたようにアンジェリークは慌てて頭を振った。
「違うの、違うの、ごめんなさい、オスカー…オスカーの言うことが信じられないんじゃないの。オスカーは優しいから、私を慰めようとしているのかと思って…だって…私、やっぱり…どんな目で見られるかと思うと…怖いの…オスカーは皆知ってるから、だから…」
オスカーはアンジェリークの背中を泣く子を宥めるように、リズミカルに撫でた。
「俺は決して君には嘘をいわない。君は綺麗だ、本当に綺麗だと思った。君の輝きも美しさも何も損われてなどいない。君の魂も、君の体も、理不尽な暴力で汚すことなどできない。汚れたりはしない。君の美しさは…宇宙一のプレイボーイと言われたこの俺が見惚れるほどなんだぜ?君は…とても綺麗だ。嘘じゃない。」
「…オスカー…」
「君が嫌なら暗くするが…でも、本音を言えば俺は君を見ていたい。君が何を気にしているかはわかるつもりだが…そう…だな、俺はこう思うんだ。いわば君は転ばされて怪我をしたようなものだ。だがそのことが君の本質を変えるわけじゃないし、転ばされた君は何も悪くない。転ばされて傷ついた君がその傷跡を気にするのもわかるが…でも、それは君自身が変わったり汚れたということではない。傷跡はいつか綺麗になるし、君という人間の本質は何も変わらず綺麗なままだ。君は何もかわってはいないんだ。そう、地中から掘り出されたばかりの宝石のように、黄金のように…表面に土がついていたり傷があるように見えるかもしれないが、その下の本来の輝きは変わらない、隠せない。表面についた傷は黄金の美しさを…その本質を決して損うことはない、傷つけることはできないんだ。その美しさも輝きも何物にも侵されることはないんだ。」
オスカーは心の底からそう思う。君の魂の輝きは何物にも犯されることはない、何物も君の高潔な魂を汚すことなどできない。君の在り方を、生き様を俺は見ているから、今までずっと見ていたから、自信を持ってそう言える。君の美しさは損われてなどいない。計り知れない悲劇を被りながら、だからこそなお、他者への共感と慈愛の気持ちを深めている君は、より深みのある美しさを身にまとい、更に透き通るように美しくなっていく。美しさとは表面の薄皮ではない。例え薄皮を取り繕ってもその内側は心有る人間には透けて見えてしまうものだ。君の魂は光を発して自ら輝いていることが俺にはわかる。その輝きが俺を惹き付け、魅惑して止まないんだ。
だが、君の魂に無理矢理つけられた悲劇の傷跡が今なお君を苦しめ、君の流した数知れないほどの涙はまだ留まる術を見出せていないのも事実だ。君の受けた傷をまったくなかったことにすることは誰にもできはしないだろう。でも、その傷に綺麗に繕いを当てて、壊れてしまう心配を減らす事はできると俺は思いたい。
「オ……」
アンジェリークは大きく瞳を見開いたままオスカーを怖いほどに見つめる。何か言おうとして口を開きかけたが、言葉がみつからないのか、声は発せられない。
オスカーはそんなアンジェリークを安心させるように髪と背中を撫で、諭すように優しく語り掛ける。
「…だが、君の心が傷ついているのは事実だ。だから俺はささやかながら、黄金の輝きを取り戻すための繕い役にでもなれれば光栄だと思ってる。君の本質は何もかわってなどいない。君の美しさは損なわれてなどいない。ただその傷はまだそこにあり、君をいまだに苦しめている。傷を負ったせいで君は自信がなくなってる、脆く壊れやすくなっている、だったら、その傷を塞いで磨きなおせばいい。そして…どこに傷があるか知っている俺にそれを手助けさせてほしいんだ…その傷を塞いで綺麗に繕いを施して、もう傷が開かないようにしてやりたいんだ…」
「おすか…あり…がとう…」
込み上げそうになる嗚咽を必死に堪えてアンジェリークは漸くこれだけ言った。
「ぶしつけに見つめてしまったすまなかった。でも、君の美しさに見惚れていたのは本当だ。君の輝きは表面についた傷なんかで損われるものじゃない。君は本当に綺麗なんだ…だが、君がもっと輝けるように、君が自分の輝きを自信を持って信じられるように…俺は君を抱く…」
「あ…あぁ…オスカー…オスカー…」
アンジェリークが自らオスカーにすがり付いてきた。オスカーはしっかりと抱きとめ、そして抱きしめた。そのままベッドにゆっくりと倒れこんだ。
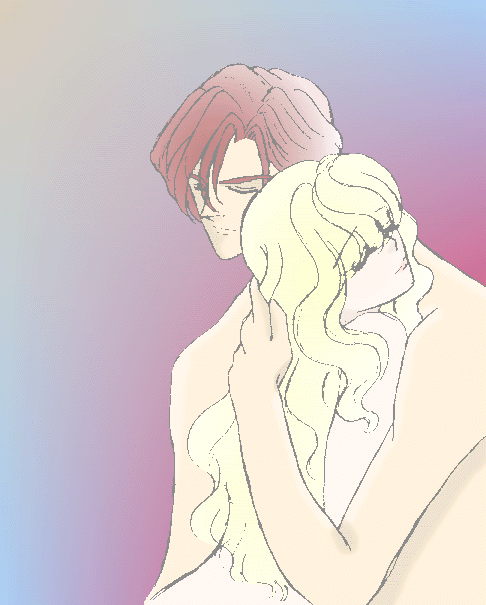
ベッドに横たわったといっても、オスカーはアンジェリークの上には覆い被さらず、横向きで彼女の体を抱きしめた。
自分が上になることは、恐らく彼女にまた理屈でない恐怖を感じさせてしまうだろう。この肉体に組み敷かれ、抑えつけられ、抗うことのできなかったあの恐怖を。
だから、オスカーは横向きに向い合わせの形でアンジェリークの体を抱きしめている。今初めて遮る物なしに肌と肌を触れあわせて。
包むように抱きながらアンジェリークの金の髪からすんなりとした背中、そして張りのある臀部までを、何度となく掌を上下させて優しく撫でさすり続けた。絹の夜着にも負けていない、いや、それ以上に柔らかく滑らかでしっとりと吸いつくような肌の感触を、飽くことなく愛でる。際限なく触っていたいと思わせるほど心地良い肌だ。
だが、オスカーはその肌触りに酔うに酔えずにいた。アンジェリークを直に抱いてみてオスカーは改めてショックを受けていた。なんと小さく華奢なのだろう。腰回りなど自分の半分もないのではないか?体つきはまろみがあって小作りでどこもかしこも柔らかくて、とてもではないが怖くて思いきり抱きしめることなどできない。ちょっと力を加えたらあっという間に壊してしまいそうだ。
そう思った途端、オスカーは無自覚に血のでるほど唇を噛んでいた。自制しなくてはと思いながら、鼻の奥がつんとしてくる。こんな華奢な小さな体で、こんな大きな男に…体重をかけられただけで身動きもできなかっただろう…力づくで押さえつけられ、無理矢理体を開かされたその惨さを思うと…
ましてや屈強な男2人がかりだ。どれほど恐ろしかったことか、苦しかったことか…その苦痛…純粋に肉体的な苦痛だけでも想像を絶する。強姦するような人間が女性の体を傷つけない配慮などする訳がないのだから。痛い…苦しい…彼女の精神が決壊した時のうわごとが、重苦しい実感でオスカーをうちのめす。
体格も力も圧倒的な男が、どうやっても抗い様のない女性を蹂躙する事の卑劣さ、卑怯さにオスカーは吐き気さえ覚える。
そして彼女は本当に紙一重で命を失わずに済んだのだという事実をひしひしと実感し、心底ぞっとした。受け入れる準備もないのに、加減など知らない、配慮も何もないこの俺と同じ肉体が思う様彼女を貪ったらどうなる?しかも一人ではなく…酷い裂傷を起こして多量に出血したり、裂傷から感染して敗血症をおこしてしまう可能性だってあったのだ。外傷の治療も受けられないあの閉ざされた塔内で…
「アンジェリーク…」
動揺を声に出さないよう渾身の精神力が必要だった。でも、呼びかけずにはいられなかった。自分と肌を重ねるという決断が、どれほど勇気を要することだったか、今更ながらに思い知った。想像を絶する苦痛を与えたこの忌まわしい肉体を受け入れようとしてくれているアンジェリークの優しさ、勇敢さ、自分への信頼…そして、ジュリアスへの想い…彼女の気持ちを思うと胸が詰まって何かが溢れ出しそうになった。
思いきり抱きしめたかった。
でも、彼女を怖がらせるようなことだけはすまいとも、固く思った。
束縛感を与えないほどに力を加減してオスカーはアンジェリークの白い柔らかな肉体を抱きしめた。唇を首筋に落した。アンジェリークの体がぴくりと震えた。
オスカーの唇がアンジェリークの首筋を滑るように降りていく。愛しげに擦りつけられる唇はあくまで優しい。時折首筋を軽く吸われ、暖かい舌を這わされたが、不快感はない。
オスカーの片手は背中に回され、泣く子をあやすように際限なく上下しては自分の背をさすっている。
もう片方の手はそろそろと首筋から胸元へ、胸元から乳房の裾野へといきつ戻りつしている。アンジェリークの肌の感触を心行くまで掌で感じようとしている、そんな動きに思えた。
アンジェリークは、オスカーに言われた通り、瞳をあけてつぶさにその様子を見ていた。
自分に施される愛撫を見つめていても、はしたないとか、いやらしい気持ち、ましてや気味が悪いなどと欠片も思わなかった。
ただ、不思議な思いがした。
オスカーの大きな掌が乳房全体をそっと包んだ。ふんわりと触れるか触れないかの微妙な感触。
もみしだくというより、円を描いて掌全体で乳房を味わうようにゆったりと撫でさすっている。
…やっぱりジュリアスの手と全然違う。もっと固い、全体に逞しくて、ごつごつして男っぽい。なのに指は長くて器用そう…それに、こんなに大きな手なのにすごく優しい…男っぽくて力強く見えるのに…
「っ!」
アンジェリークは突然大きく肩を震わせ、長い呼気に怯えを吐き出した。強い力…力強く見える手…まさに万力で締め付けられたような…そのまま折られるかと思ったほどの手首の痛み…その痛みが突然フラッシュバックした。
「アンジェリーク?」
オスカーの手の動きが止まった。
「オスカー…オスカー…お願い、オスカーの手で私のほほに触れて?」
オスカーはアンジェリークの瞳を見つめたまま言われた通りにその頬を両手で包みこんだ。その上にアンジェリーク自身の手が重なる。
「あったかい…やさしい手…大きくて優しい手…オスカーの手…」
「ああ、そうだ。これが俺の手だ。感じてくれ。君を慈しむためにある俺の手だ。」
「ん…ごめんなさい、もう平気…オスカーの手は…安心できるから…私を何度も助けてくれた手だから…」
「そのためにこそ、俺はここに居る…」
再び口付ける。乳房を包みこむ。やわらかく捏ねるようにもみしだく。平坦だった先端が少しづつだがオスカーの掌に存在を主張し始めた。
その反応を見取り、オスカーはそっと…ほとんど力を込めずにその先端を指の腹で転がしてみた。
「ん…」
塞いだ唇から僅かに吐息がこぼれた。
オスカーは背中に回した手を解き、両手で乳房を包みこんだ。掌全体でやんわりと先端を刺激しながら、時折、触れるか触れないかの力加減で指の腹で先端を擦った。
「ん…んふ…」
明かに乳首が固くたちあがってくる。漏れでる吐息に艶が混じり始めた。オスカーは尖りはじめた先端を軽くつまんで指先でよりあわせてみた。視線を下にやれば、可憐に色づく先端は花の蕾のようで、もっと存分に愛されることを待っているかのようで。早く口に含んで一杯愛してやりたい…そう思わずにはいられない愛らしい蕾だった。
オスカーは口付けを解き、唇を首筋から胸元へと何度も往復させた。
よせては返す波のように、でも、少しづつ潮が満ちていくように、唇を徐々に乳房の裾野へからこんもりと盛り上がった稜線へと伸ばし、乳房の触感を唇で確かめて行く。
唇を押し当てると、乳房はほんわりとした弾力でオスカーを一度受けとめ、そして跳ね返す。何度も両の乳房全体に唇を押し当てていくうちに、指先でそっと摩っていた乳首もすっかり固くなっているのを感じた。
『こうしても…大丈夫だろうか…』
その懸念はあったものの、オスカーはもう堪えきれずに、乳首に軽く口付けた。含みも吸いもしない、本当にその先端に閉じた唇で軽く触れてみたのだった。
「う…」
アンジェリークがぴくりと反応した。でも、緊張した様子はない。自分を押しのけようとも、逃げようともしない。
オスカーは胸の中で安堵の息をはきながら、軽く口を開けて唇で乳首を鋏んで、その弾けるような弾力を味わった。このかわいらしい蕾を思いきりかわいがってやりたい…オスカーは思うと同時に乳首を口に含み、舌先でつつき、舐め上げ、転がし、弾いた。
「あ…」
アンジェリークが悩ましげに身をよじった。綺麗な眉がきゅっと潜められ、無意識にであろうが、瞳が閉じられた。
その表情に安堵する一方で、オスカーはどうしようもなく自分の内部で燃えあがるものを感じた。
拒否されないだけでも嬉しかったのに、自分の愛撫を僅かでも心地良く思ってくれたのか…歓喜に目がくらみそうだ。なら…俺はもっと君を愛していいのだろうか。君は少しでも悦びを覚えてくれるのだろうか。もし、君が悦びに我を忘れてくれたら…
虫のいい期待はするな…冷静になれと自分に語りかける声を遠くに聞きながら、オスカーは改めてアンジェリークの乳首を深く含みなおした。ねっとりと舌を絡めるように舐め上げ、乳首の固く締まった弾力を心行くまで味わうように舌先で弾いては微かな甘噛みも時折加える。
「あん…んふぅっ…」
アンジェリークが素直すぎるほどに官能の悦びを表す。
『だめ…だ…』
その艶やかな吐息が炎を煽る。アンジェリークの細い腰に腕をまきつけるようにしてきゅっと抱きすくめた。アンジェリークの背が軽くしなった。突き出される形になった乳房に顔を埋めるようにしてオスカーはその先端を交互に執拗なまでに吸いあげた。愛撫がきつくならないように、自制しなければとは思いながら。
しかし、口戯を加えるごとに耳に途切れ途切れに届く荒い吐息と喘ぎに、オスカーはいつしか夢中になって乳房を愛撫していた。せずにはいられなかった。
明かにアンジェリークは快感を得ているようだった。
この俺の愛撫に…悦びをもって応えてくれている…そう思うだけで頭が真っ白になってしまう。今よりもっと悦ばせてやれたら…その思いだけに思考が染められていく。
オスカーは乳首に軽く歯をあてながらその先端に舌を縦横に踊らせた。柔らかいのに張りのある乳房を揉みしだいてはその感触に耽溺していく自分をオスカーはもう止められなかった。
オスカーの舌が乳房全体に這わされているときは、まだ、余裕をもってそれを見ていられた。
そう…オスカーの唇が舌が…少しづつ、私を宥めるように触れてくる…暖かい…優しい…私を怖せないように、ゆっくりゆっくり…そう、まるで私を壊すのを怖れているみたいに…
でも、その唇が乳房の先端に触れた時、戦慄が走った。本当に純粋に触れただけだった。アンジェリークは自分が一瞬嫌悪を感じてしまったのかと思ったが、そうではないようだった。嫌な気分が残らなかったから。でも走った感覚は鮮烈すぎてそれが何なのかよくわからなかった。
オスカーは暫時そのまま動かなかったが、間を置いてから大丈夫と断じたのか先端に緻密で濃密な愛撫を加え始めた。
敏感な先端にオスカーの舌の先が触れて…絡まって…弾かれて…鋏まれて…きついと感じる寸前の激しさかと思うと、時折はっと気付いたようにその愛撫が物足りないほど穏やかにもなる…振り子のように振幅のある愛撫…
や…どうしよう…私、変……声が出そう…オスカーの唇も舌も暖かくて優しいのに、どこか激しい、熱い…やるせない感覚が胸中に降り積もっていく。
思わず瞳を閉じた。何かに流されそうで怖かったのか、それとも、その感覚をもっと鋭敏に感じてみたくて瞳を閉じたのか、アンジェリークは自分でもわからなかった。瞳を閉じたらオスカーの舌の動きがより生々しく感じられたからだ。もう堪えられず声が出てしまった。
途端にオスカーにきゅっと抱きすくめられた。音をたてて乳首を吸われた。舌先が乳首の先端を踊るように弾くたびにどうしようもなく鋭い快感が背筋を走りぬけた。
ああ…私……心地良いって感じてる……だってもう、声が抑えられない…
自覚してしまったらもう抑えられなかった。背が撓る。吐息とも喘ぎともつかない音が口から零れる。するともっとオスカーの愛撫が激しくなる。オスカーの唇から、自分を抱きしめる腕の力から、オスカーの懸命さが伝わってくる。オスカーの真摯な想いが体を熱くする。
あの…同じ顔をした男の舌はただおぞましいだけだった…私の体中を這いずって……気持ち悪い…汚らしい…ぞっとする…でも動けない…顔を背けるので精一杯…何をされても…何をされているかわかっていても押しのけることさえできなかった…野卑な声で聞くに耐えないことを言って…耳を塞ぐこともできない…あれがこの優しい唇と同じ唇のわけがない…
「いや!」
アンジェリークは思わず大きな声をあげてしまった。
「っ!…」
オスカーが弾かれたように体を離した。酷く傷ついたような表情が瞬間浮かんだ。
オスカーは自分に舌打をした。
自制できずに、思いきり愛撫を加えていたという自覚があったから。
彼女の艶やかな声に求めらているように錯覚してしまった。馬鹿だ、俺は…俺が彼女を悦ばせることができるなどと一瞬でも期待して…激しい愛撫など加えれば怯えるのは必定なのに…
「すまない…夢中になっちまった…怖がらせてすまなかった。嫌ならもう…」
嫌悪か恐怖か…そんな表情を浮かべているかと思うとアンジェリークの顔が見られず、オスカーは目をそらしたまま、アンジェリークの体を手放そうとした。
「あ!違う!違うの!オスカー!」
アンジェリークがオスカーに思いきり抱きすがってきた。
「アンジェリーク…」
オスカーは何が何だかわからずアンジェリークを抱き返すこともできずに硬直した。
「嫌って言ったのはオスカーのことじゃないの!同じ唇のはずなのに…全然違うって思ったら…オスカーの唇は優しくて暖かくて気持ちいいのに…アレは…ナメクジか蛇に肌をはいずられてるみたいだった…ぞっとするほど冷たくて、おぞましくて、たまらなく気持ち悪くて…オスカーの唇と全く違うって思ったら一緒にそれを思い出しちゃったの…オスカーが嫌なんじゃないの…」
オスカーは今聞いた言葉が信じられなかった。
「すまん、聞き間違いじゃなければ…俺の事は嫌じゃないと言ってくれたの…か?」
「ん…同じ体だなんて信じられないって思ったの…そう思ったら一緒にあれを思い出してしまったの…でも、全然違う…本当に全然違う…オスカーは…オスカーにしてもらうことは安心できて…あ…ごめんなさい…私、声、抑えられなくて…はしたなくて呆れた?ごめんなさい…」
消え入るような声で顔を俯かせてしまうアンジェリーク。肩を小刻みに震わせるアンジェリークをオスカーは思わず思いきり抱きしめてしまった。
「な!…そんなこと思ってもいない!アンジェリーク……なんでそんなことを思う?俺は…俺はその何を言ったらいいのか…すまん、頭の中がごちゃごちゃして…その…」
上ずってしまって上手く言葉がでない。俺の愛撫が嫌だったのではなかったのか。俺の愛撫は気持ちいいと思ってくれ、その対比でおぞましい記憶が触発されただけだと。全然違うと…そう思ってくれたのか…
「オスカー?」
おずおずと怯えたように自分の名を呼ぶアンジェリークにはっと我に返った。大きく一度深呼吸した。
「すまない、不安に思わせて…その…俺は君が少しでも心地良くなってくれたらしいと知って、その…感動で呆然としちまったんだ…嬉しかった…俺に嫌悪を抱くどころか、僅かでも…その…気持ちよく感じてくれて…嬉しかったんだ…呆れるわけなんてない…あんまり嬉しくて頭がどうにかなりそうだ…あ、その…俺がアレとは全然違うと思ってくれて…」
「ん…オスカー…私、オスカーの言ったことが、わかった…全然違う…同じ状況で同じような事をしてみればその違いがわかるって…今、すごくよくわかる気がする…」
「それなら…続けてもいいだろうか?…その…もっと、俺のことをわかってもらいたいんだ…俺は俺でしかないと…」
「オスカー…私こそ…驚かせてごめんなさい…また、突然嫌って言ったり暴れたりするかもしれないけど、それはきっとオスカーにじゃないの、だから…」
「ああ…わかった…それなら…そんな嫌な思い出も蘇らないほどに…俺のことを感じればいい…何も他の思考など割り込む隙がないほどに、俺を感じてほしい…」
「え?」
オスカーは何も言わずにアンジェリークを抱きしめ、唇を重ねた。舌先でアンジェリークの唇を割ると、アンジェリークもその意を察し、おずおずと口を開けてくれた。オスカーは初めてアンジェリークの口腔内に舌を差し入れ、アンジェリークのそれを絡めとった。強く吸った。
「ん…んふ…んく…」
いきなりの激しい口付けをアンジェリークは戸惑いながらも受けいれた。深い口付けを拒まれなかったことにオスカーは更に決意を固める。
『もう、遠慮はしない……躊躇いがちの愛撫は却って君に忌まわしい思い出を呼び起こしてしまうから…君は俺の愛撫を心地良いものと受け入れてくれたから…もっと気持ちよくしてやりたい…何もかも忘れるほどに…それをもってわかってほしい。俺は俺だということを。俺以外の何物でもないということを。』
決して強い力では抱きしめない、少しでもきつく感じるようなことはしない。それは改めて自分に戒めた。
だが、もう愛撫自体は自制しない。君の心の求めるままに、君が少しでも心地良くなってくれるように、俺は…迷わず君を愛する。
オスカーは、アンジェリークの胸の谷間に自分の顔を一度愛しげにすりつけると、すぐさま乳首を口に含み、舐め上げ、弾き、転がし、吸い、微かに噛んだ。
切なげな声が間髪をいれずにあがった。